
大学3年生の理系のあなた、行きたい研究室は決まっているでしょうか?

難しいので研究内容では判断できない…けどハズレ研究室は絶対やだ
こう考える3年生は非常に多いです。
そこでこの記事では、研究室の失敗しない選び方をこっそり11個教えます。すべて機械の大学院生(M1)の体験談によるものです。
早めに研究室選びのコツを知って、自分の希望通りの研究室にいけるように戦略を立てていきましょう。
研究室を選ぶことは大学選びよりも大事な理由
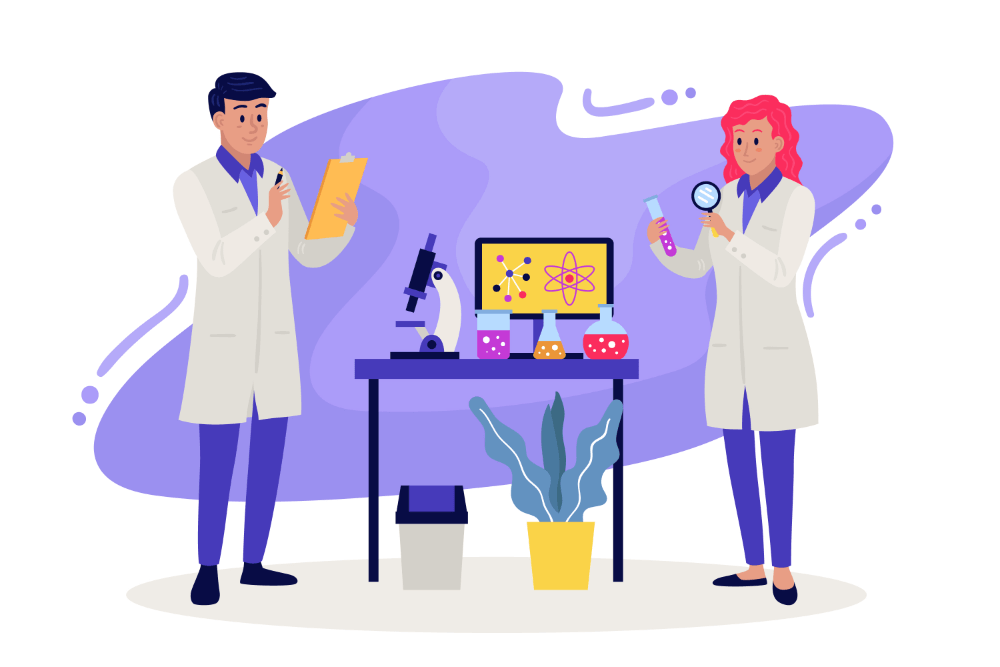
理系大学生にとって研究室生活は超重要。
なぜなら研究室の教員や研究業績によって将来の就職先に大きな影響が出るから。
大学受験に少々失敗してワンランク下の大学に入学したとしても研究室がよければ就活はうまくいきやすいです。
逆に大学受験がうまくいっても、ブラック研究室を引いてうつ状態になり卒業もままならないという方もいます。
なので正直、研究室を選ぶことは大学選びよりも大事だと感じました。
また研究室とは1日の大半を共に生活するシェアハウスのようなものなので、先生や同期、先輩と雰囲気が合わないとかなりしんどいです。

さらに研究室は短い人で1年、大学院まで行く人は3年を共にします。
じっくりと吟味しましょう。
ではどうやって研究室を選んだらいいのかを11個の観点から詳しく紹介していきます。
研究室の失敗しない選び方11選【経験談】

先にさっと全体の内容が見れるように、下記に11個まとめました。
気になるところからチェックしてみてください。
- 教員の人柄を知る
- 先生の研究方針を聞く
- 企業と合同研究しているかチェック
- 先生の出張が多いか確認する
- 実験のスタンスを確認する
- 研究室ホームページは更新されてる?
- 研究室訪問をする
- 先生が研究、院試勉強、卒業、就活のどれを優先しているかを確認する
- コアタイムがあるか聞く
- 研究室の大きさ・設備を確認する
- 研究室卒業生の就職先を聞いてみる
教員の人柄を知る
研究室選びで最も重要なことは、教員の人柄です。
どんなに成果を出している優秀な先生でも人柄や雰囲気が合わないと今後すべてが終わります。

中には平気で学生の人格否定をしてくる教授も。
「興味ある研究している研究室があるけど、先生と話した感じあまり合わないかも…」と思った場合、その研究室は辞めておく方が無難です。
先生の研究方針を聞く
先生の研究方針はしっかりと聞きましょう。成果主義なのか、研究室に毎日来ることが重要なのか…などなど。
教授の先生の中には、半分自分の趣味・興味で研究している人もいます。
ですので、教授の興味だけで研究していると、自分の卒論・修論が書きにくいテーマの場合があります。振り回されるかも。
あるいは准教授の先生は、教授に昇格するために学生にどんどん実験させて論文を書こうとしている先生もいます。(※一応弁明しておきますが、これは全然悪いことではありません)
なので先生の研究方針はしっかりと聞きましょう。
企業と共同研究しているかチェックする
一見、「企業と合同研究している」って言うとかっこいいですよね。
しかし僕の意見としては、企業と合同研究している研究室はおすすめしません。
なぜなら共同研究していると、あなただけにものすごい負担がのしかかってくるケースがあるから。
だって企業側は研究室にお金を払っているわけですので、実験結果の提出を急かしてきます。
先生の出張が多いか確認する
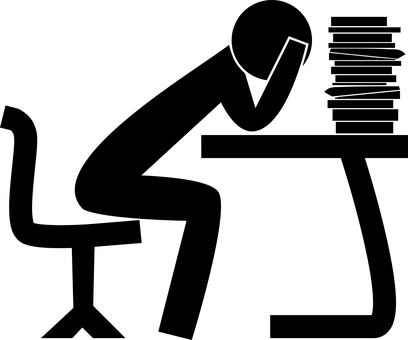
企業と共同研究してる先生の場合、多忙でなかなか大学にいない人もいます。
そういう先生の場合、実験の細かい打ち合わせがなかなか出来ず、研究のスピードが遅くなり、卒論シーズンに大慌てになる可能性があります。
ふだんは暇ですが、最後に急に忙しくなるタイプです。
実験のスタンスを確認する
実験のスタンスは2種類あります。
①:同じものを研究室メンバーで協力して作るパターン
②:各自テーマが与えられ独立して実験を進めていくパターン
①は全員でロボットのような機械を作るというようなイメージです。
あるいは、先輩と後輩がペアーになって2人1組で研究することもあります。
優秀な先輩に当たれば勝ちゲーですが、後輩をパシリに使うような人が上司になるとかなり辛いです。
①は、頑張っても頑張らなくてもさほど差がないため、モチベが下がるようなイメージがあります。
※重い荷物を数人で持つとき必ず1人は手を添えているだけのやつがいるのと同じパターンですね。笑
②は完全に個人プレーです。頑張る人と頑張らない人の二極化が激しくなります。
これは人それぞれですが、僕のおすすめは後者です。自分で物事を解決する力が身に付きます。
研究室ホームページは更新されているか?

まずは気になる研究室のホームページがあるか、更新がされているか確認しましょう。

研究室行事の更新が2年前とかで止まっていませんか?
更新が止まっている研究室は注意しましょう!研究成果が出ていないなどの理由が考えられますね。
※ホームページ作ってない研究室もたくさんありますので、こちらは参考程度に。
研究室訪問をする
是非アポを取って気になる研究室の訪問に行きましょう。
そしてその研究室の先輩にストレートに以下の2つの質問をしましょう。
1.どうしてこの研究室を選んだんですか?
2.この研究室の嫌なところは何ですか?
いいところだけでなく、悪いところを聞いておくのがポイントです。
入ってからのギャップが無いようにしておきましょう。
また、次のような質問もいいと思います。
「他の研究室で悪い噂が多い研究室はどこですか?」
実験スケジュールが過密過ぎたり、授業ではいい顔していた先生に裏の顔があったり…色々あります。
ぜひ色々と先輩に聞いてみてください。
先生が研究、院試勉強、卒業、就活のどれを優先しているかを確認する
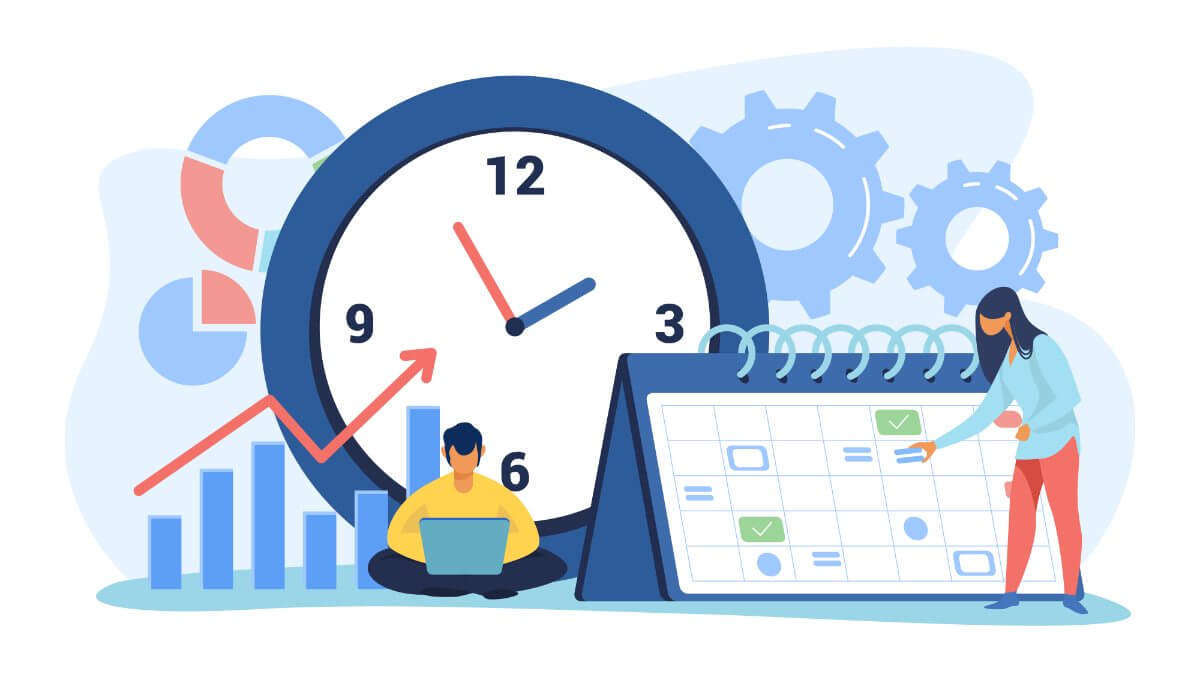
学生想いの先生だと、就活時や院試勉強期間中は実験をストップにしてくれます。
しかし友だちの研究室では、院試勉強期間中も実験していたそうです。
その先生曰く、「実験と院試は別。日中は実験して、院試勉強は夜に自分の家でやりなさい。」
正直かなり鬼畜です。専門10科目もあると夜少し勉強しただけでは合格する確率は低いでしょう。院浪人することになるでしょう。
コアタイムがあるか聞く
※コアタイムとは、必ず研究室にいなければならない時間のこと。
コアタイムがある研究室は、9時-17時は研究室に行かなければならないそうです。
バイトのようにタイムカードを押して管理している研究室もあるそうです。
(※ちょっとそれはどうかなと疑問に思います。そこまで管理されると僕はかなりストレスです。)

ちなみに僕が入った研究室はコアタイムがありません。
自分で実験のスケジュールを組むので、ある時は朝8時から実験開始したり、夜までしたりすることもあります。土日も実験行うことが多いです。
しかしその逆で、やること終わっていれば平日1日まるまる休んで出かけたりもします。
僕はフレキシブルな生活スタイルの方があっていると思ったのでこの研究室を選びました。
研究室の大きさ・設備を確認する
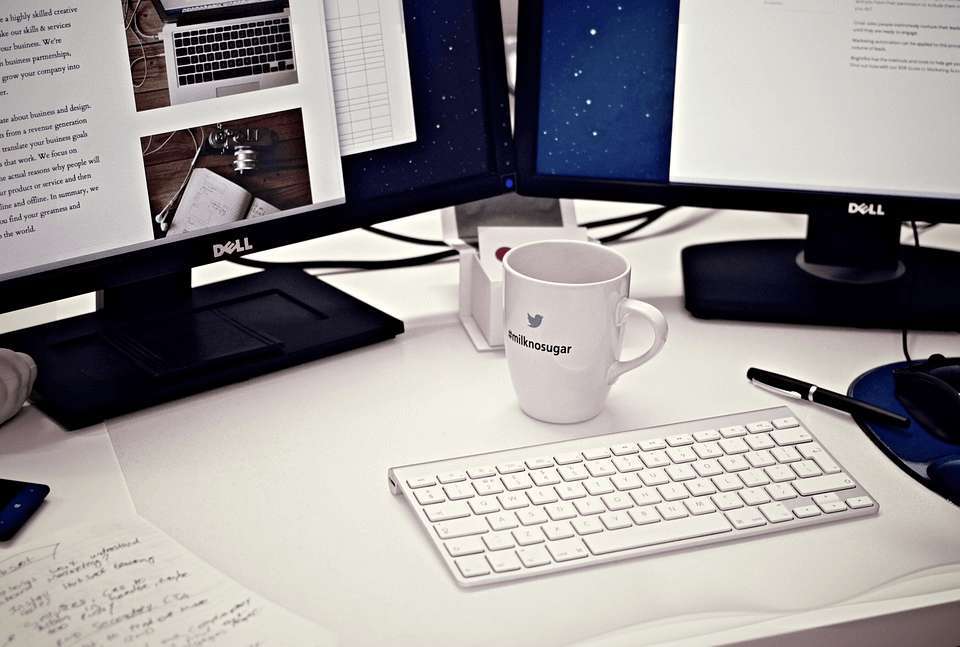
研究室は第二の家になります。
家を選ぶときは広いのか狭いのか、きれいなのか汚いのか、備品は揃っているのか確認しますよね。
研究室を選ぶときも家を選ぶのと同じような感覚です。
広い部屋だと、一人当たりの机も広くなりかなり快適な暮らしができます。
また、デスクトップパソコンやモニターを貸してくれるのかも検討していいでしょう。
大画面で快適にYouTubeが見れます。笑
冷蔵庫や水道、電子レンジ、ソファーなどがあるとなお良いでしょう!
モニター2枚はかっこいいですよね笑
その研究室の卒業生の就職先を聞いてみる
卒業した先輩がどのような会社に就職したのか聞いてみましょう。
大手なのか中小なのか、研究内容と同じ職種なのか全く別なのか、これを聞いているのと聞いていないのでは大違いです!
研究室の選び方まとめ
- 教員の人柄を知る
- 先生の研究方針を聞く
- 企業と合同研究しているかチェック
- 先生の出張が多いか確認する
- 実験のスタンスを確認する
- 研究室ホームページは更新されてる?
- 研究室訪問をする
- 先生が研究、院試勉強、卒業、就活のどれを優先しているかを確認する
- コアタイムがあるか聞く
- 研究室の大きさ・設備を確認する
- 研究室卒業生の就職先を聞いてみる
以上です、少しでも研究室選びの参考になれば嬉しいです。
ちなみにうちの研究室の方針は、学生が論文を書き国際発表を行い、将来活躍できるエンジニアになってもらうことだそうです。
「うちは研究大変だけど頑張ったら頑張った分だけ自分に返ってくる研究室だよ」と言われたのが印象的で今の研究室を選びました。
ぜひ大学院生についてや研究室生活の記事も見て行ってください↓



